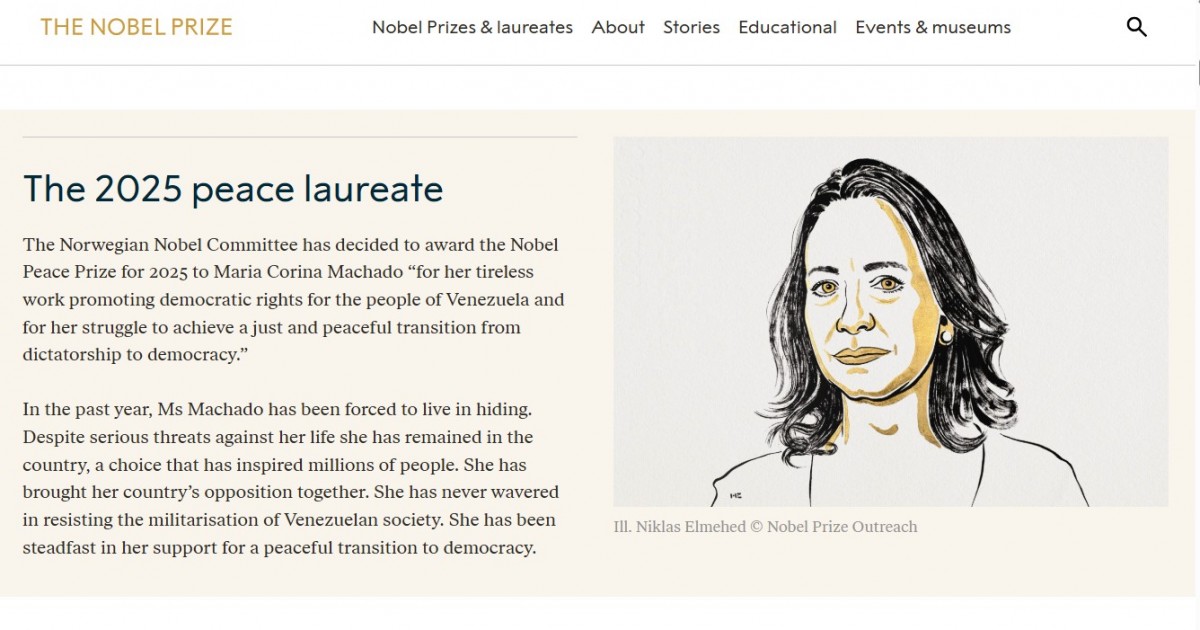フェイクだらけの「平和主義」、日本にも有害―ウクライナから問う憲法9条の真価

ロシア軍に攻撃を受けた村 今年2月ウクライナ東部にて筆者撮影
フェイク(偽情報)やプロパガンダが現実を浸食し、戦後の日本の安定と繁栄の礎となった基本原理すら脅かそうとしている―ロシアによるウクライナへの全面的な侵攻が始まってから、「日本の良心」とも言える市民社会に深刻な分断が起きています。
日頃、「基本的人権の尊重」や「平和主義」といった日本国憲法の原理を尊び、これらの原理をより具体的に実現することを求めてきた人々の一部、そうした価値観に基づき発信を続けてきたメディアの中に、ロシアを擁護し、ウクライナをバッシングするという、不可解な動きがあります。これらは米国のトランプ政権の動向もあり、より活性化するのかもしれませんが、単にウクライナの人々に対して暴力的な言動であるだけではなく、中長期的に見て、日本の平和そのものをも揺るがすものになりかねません。
この2月、侵攻開始から3年のウクライナを取材した後、改めて日本におけるウクライナ侵攻に関する議論を見つめ直した際、とりわけ情報戦という点において、ロシアのプロパガンダの害は、単にウクライナにだけに向けられたものではないと実感しました。
本稿では、ウクライナ取材で聞いた現地の人々の声も交えつつ、トランプ政権が進める「停戦」の問題点や、なぜウクライナを見捨てることが日本にとっても極めて大きな問題となり得るのかを論じていきます。
【志葉からのお知らせとお願い】ウクライナやパレスチナなどの紛争地での現地取材や地球温暖化対策、脱原発、入管問題などで鋭い記事を配信し続けるジャーナリスト志葉玲が、ジャーナリズムの復権と、より良き世界のための発信をテーマにニュースレターを開始。本記事含め、当面、無料記事を多めに出していきます。お知らせのための登録だけなら無料ですので、是非、以下ボタンからご登録ください。Journalism will never die!!
〇トランプ政権に呼応、朝日新聞編集委員のコラム
筆者が本稿の執筆を思い立った直接のきっかけは、朝日新聞GLOBE+に掲載された、同紙の副島英樹・編集委員によるコラムです。

🌎ウクライナ戦争で即時停戦言わず、世論煽った日本メディア globe.asahi.com/article/156322… ウクライナ戦争で即時停戦言わず、世論煽った日本メディア 被爆地・広島で感じた怖さ:朝日新聞GLOBE+ ウクライナ侵攻が始まってから3年を迎える。この間、戦争の愚かさを知るはずの被爆国日本のメディアは「戦え一択」と言わんばか globe.asahi.com
このコラムは、ロシアに都合の良い主張に基づいてウクライナ側の抵抗を否定するもので、さっさと妥協して停戦すれば全て解決、そうしないウクライナの側こそが悪いと言わんばかりの内容です。副島編集委員のコラムの趣旨は「非核・非戦」がテーマであるようなのですが、そこに、当事者であるウクライナの人々の視点は一切ありません。
副島編集委員のコラムで引用されている「識者」達の主張に対しては、これまでも筆者はその問題点を指摘してきました。作家・外務省元主任分析官の佐藤優氏の主張の危うさについては、こちらの記事で詳しく書いています。

reishiva.theletter.jp/posts/f50d61a0…
#NHK が元外交官で作家の #佐藤優… 「佐藤優クロ現問題」でNHKに批判相次ぐ―世論分断工作に加担?ウクライナ取材のジャーナリストが解説 NHKが、元外交官で作家の佐藤優氏のインタビューを報道番組『クローズアップ現代』やウェブニュースで大きく取り上げたこと reishiva.theletter.jp
佐藤氏は、「命は大切」と一見、良いことを言っているように見えますが、ウクライナ首都近郊ブチャの市民をロシア軍が虐殺したことについては、「ブチャに関しては、私は確信をもったことは言えない。というか、関心がない。要するに、戦時中における虐殺事件とか、強姦事件に関する報道は心理戦の一部」と言い放つなど、ウクライナ側の被害を軽視し、ロシア側の主張に同調する姿勢が目立ちます。なお、「ブチャ虐殺はウクライナの自作自演」という主張はロシアが盛んにしていますが、BBCやNYタイムズのファクトチェック、そして筆者のブチャ取材から言っても、ロシアの主張はフェイクそのものです。
また、やはり上述のコラムで紹介されている、伊勢崎賢治氏や和田春樹・東京大名誉教授らの主張する「今すぐ停戦を」の問題点についても、記事を書きました。

news.yahoo.co.jp/expert/article…
#ウクライナ 「平和」を訴える知識人達の歪み―イデオロギー優先の「即時停戦」論 #ウクライナ #日本国憲法(志葉玲) - エキスパート - Yahoo!ニュース 先日、筆者がYahoo!ニュースに寄稿した記事"ウクライナを踏み台に「平和」を語るリベラル知識人の貧困"は、特にSNS news.yahoo.co.jp
伊勢崎氏らは、「ウクライナで起きていることは欧米の対ロシア代理戦争だ」と決めつけますが、こうした「代理戦争」論は、ウクライナの人々の主体性を否定し、さらには、「戦争を望んでいるのはロシアではなく欧米(と、その手先であるウクライナ政府)の側」だとして責任の所在をすり替える、極めて差別的かつ暴力的なロジックです。そして、こうした「代理戦争」論は、ウクライナ侵攻を「欧米の攻撃からロシアを守るための特別軍事作戦」と位置付けるプーチン大統領のプロパガンダとの親和性が極めて高いことにも注意が必要でしょう。実際、ロシア寄りのトランプ政権ではルビオ国務長官が今月6日、「ウクライナを支援する米国とロシアの代理戦争」と発言し、これをロシア側が歓迎するやりとりがあり、いよいよフェイクが現実を侵食していると国際社会に印象付けさせました。
副島編集委員のコラムは、特に目新しいものではなく、これまでの「即時停戦」派の主張の繰り返しなのですが、正にトランプ大統領政権の米国がロシアの側に立ち、剥き出しの弱肉強食の論理でウクライナを追い詰めている最中に、それに呼応するようなコラムが書かれ、日本を代表するクオリティペーパーに掲載されるということ自体が酷いことです。
ウクライナ侵攻の開始当初から、ロシアが発信するプロパガンダは日本のネットやメディアも侵食していますが、情報戦という点において、「攻撃」を受けているのは、ウクライナのみならず、日本を含む民主主義陣営全体であることを改めて認識すべきでしょう。
〇ウクライナで人々の声を聞く
メディア人であれば、ウクライナのことを論じるのであれば、やはり、現地に行き人々と対話すべきです。この2月、筆者はウクライナを訪れました。ロシア寄りの姿勢が目立つトランプ政権の主導する「停戦」について聞くと、やはり否定的な意見が多く聞かれました。
「トランプ大統領は『停戦』の見返りにウクライナをロシアに差し出そうとしているように見えます。ゼレンスキー大統領は正しい。彼は私達の国益を守り、領土を守り、(レアアースなどの)資源を守ろうとしています。(トランプ政権が「ウクライナは大統領選を行うべき」*としていることについて)、新たな大統領になるとしたら、ゼレンスキーほど毅然とした対応をとらないかも知れず、それをとても恐れています。」(20代男性/学生)
*ウクライナの法律では戦時中は大統領選を行えない。
「『停戦』についての意見は、私達の家族にこの間に起きたことが全てです。残念ながら、トランプ大統領の交渉には論理がありません。私達の家族は2人を失いました。弟は戦死し、義父は行方不明です。心の痛みなしには、このことを話すことができません。声が震えてしまいます。全世界に向かって叫びたいです」(30代女性/戦死者遺族)
「私達は落ち着いて反応をすべきです。トランプは、米国全体ではありません。米国の国民の反応を見れば、彼らがトランプの政策に賛成していないことがわかります。ですから、最終的には全て上手くいくと思います」(40代男性/兵士)。
他方、「僕の友人達は何人も兵士になって、皆、死にました。停戦が良いか悪いかは別として、もう辛すぎて限界です」(20代男性/メディア関係)と、「停戦もやむなし」とする人々もいましたが、彼らとて、トランプ大統領のやり方を積極的に支持している訳ではなく、ましてウクライナがプーチン大統領の傀儡国家になることは望んでいません。「ウクライナがロシアのような国になるのは嫌です。僕達はユーロマイダン*をとても誇りに思っています。まだまだ改革は道半ばで、それはもっと進めていくべきですが、ともかく、僕達が選んだ道は正しいものです」(同)。
*ユーロマイダンとは、腐敗した政治の一掃や、自由や民主主義、そしてEUとの関係強化を求め、人々が起こした市民革命。2014年2月、当時のウクライナの大統領で、プーチンの傀儡のヤヌコヴィッチはロシアへ亡命。市民側の勝利となったが、同時にそれはプーチンの逆鱗に触れ、ロシアはウクライナ南部クリミアを併合し、東部ドンバス地方への軍事侵攻を開始する。なお、ロシア側のプロパガンダでは、ユーロマイダンは「米国が煽ったクーデター」という扱い。

マイダン(独立記念広場)には戦死者を弔う無数の旗が立つ ウクライナ首都キーウにて筆者撮影
断腸の思いで「停戦もやむなし」とする人々に実際に会って対話した筆者としては、そうした人々の状況も考慮せず、単なる世論調査の数字や断片的なコメントだけをとりあげて、「ほら見ろ、やはり抵抗なんかするべきじゃなかったんだ」と、したり顔をする日本の自称「平和主義者」程、グロテスクなものはないと思うのです。
〇「停戦」で占領下の人権侵害が深刻化?
今回の取材で特に印象に残ったのは「占領は戦争より悪い」(筆者の友人であるウクライナ人談)ということです。今回、筆者は、ウクライナ南部や東部からの避難民の人々や、それらの地域でロシア軍に捕まった人々の家族達、現地人権団体のメンバーらにも話を聞きました。ロシア軍の占領下では、極めて不条理かつ深刻な人権侵害―例えば、自宅にウクライナ国旗があったことから「スパイ容疑」をかけられ、出鱈目な裁判の挙句、10年半の懲役刑にされたりするなど―が頻発し、人々は安心して暮らせないとのことでした。

ロシアに拘束された民間人イリーナ・ホロブソヴァさんの解放を求める御両親 筆者の取材にオンラインで対応
ロシア軍に拘束された人々は、民間人、兵士を問わず、そのほぼ全員が激しい拷問を加えられ、命を奪われたケースもあります。こうした不当拘束や拷問の被害者は「数万人規模でいる」(ノーベル賞受賞の人権団体「市民自由センター」)とのことです。
さらに、占領下の学校に通うことは子ども達にとって、大きなリスクになります。ロシアのプロパガンダ教育が行われるだけではなく、学校の夏季合宿に参加した子ども達が、ロシア本国やロシアが併合したクリミア半島に連れ去られ、行方不明になるということも相次いでいるとのことです。実際、筆者のインタビューに対し、そうした具体的な事例を話してくれた避難民の人がいました。
避難民の人々や、ロシア軍に捕まった人々の家族達、現地人権団体のメンバーらが危惧するのは、これらの人権問題がトランプ大統領主導の「停戦」の交渉の中に含まれていないということです。ウクライナからのロシア軍の全面的な撤退ではなく、現在、ロシアがウクライナ東部や南部の各地域を占領したままでの即時停戦は、占領の固定化につながりかねず、そこで様々かつ深刻な人権侵害が続く可能性が極めて高いという問題があるのです。
〇日本国憲法の原理を否定、「平和主義者」の矛盾
なぜ、ウクライナの人々はロシアの侵攻に対し抵抗しようとしているのか。それは、自身や家族の命と安全、人権と民主主義をロシアから守るためです。これらのことは、日本国憲法の原理のうち、「基本的人権の尊重」や「国民主権」と、ほぼ同義と言えるのではないでしょうか。「命があるだけマシ」とウクライナの人々にただただ「即時停戦」だけを押し付けることは、本当の意味での平和主義とは言えません。停戦交渉を進めるにしても、ウクライナの人々の人権や同国における民主主義を守るという条件は絶対に必要です。
ロシアの横暴を許すことは、ウクライナにとってだけでなく、日本にとっても非常に大きな問題となり得ます。国際紛争の解決の手段としての戦争を放棄した日本国憲法第9条は、必然として、「法の支配」に基づく国際秩序に大きく依存します。侵略戦争は国連憲章で禁じられており、一般市民を殺傷することは国際人道法に反する戦争犯罪です。これらの法秩序を蹂躙しているのが、ロシアによるウクライナ侵攻であり、こうした横暴を許すのであれば、憲法第9条も危うくなります。憲法を尊ぶ平和主義者であるのならば、ロシアを擁護しウクライナを叩くといった振舞いは、深刻な自己矛盾となるのですが、残念ながら、「護憲派」を自認するリベラル・左派の人々(含む著名人、有識者)にも上述のような自己矛盾に陥っている人が少なからずいます。
〇問われる9条の真価
上述のような自己矛盾に陥ってる人々は論外として、9条を中心とした日本の平和主義は、ともすれば、自国民の安全にばかりに比重を置きすぎで、それは「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に追放しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたい」「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という憲法前文を現実の世界に反映するということにおいて、成功しているとは言い難いものがあります。
日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞したように、日本の反核運動は世界において重要な役割を果たしていると言えますが、だからこそ、「核の脅威」を背景に侵略戦争を続けるロシアを許してはいけないのです。まして、ウクライナは同国の安全保障を米国とイギリス、ロシアが担うことを条件に核を放棄したという経緯があります(ブダペスト覚書、1994年)。そのウクライナを見捨てることは、「やはり核兵器を捨てたことは失敗だった」との前例を作り、日本の平和主義が目指す「核なき世界」の実現を遠ざけることになりかねません。
日本は憲法上の制約もあり、軍事面でウクライナを支援することはできません。だからこそ、ただ「平和を祈る」だけではなく、非軍事の手段でいかにロシアの暴走を止めるかを、もっと真剣に模索し、行動すべきです。例えば、ロシアの重要な収入源として、原油や天然ガスの輸出がありますが、これを封じ込めることにより戦争する国力を奪うことは、日本が外交としてできることではないでしょうか。実際、スウェーデンやフィンランド等の欧州6カ国は、ロシア産原油に課されている1バレル=60ドルの価格上限をさらに引き下げるよう欧州委員会に求めています(関連情報)。これは、ロシアの原油収入を減らし、戦争の資金源を減らすための措置です。こうした動きに日本としても積極的に関わるべきでしょう。また、欧州はロシア産原油や天然ガスへの依存を減らし、風力や太陽光等の再生可能エネルギーに切り替えていますが、日本としてもそれに習うべきです。さらに、中国やインド、トルコなどロシア産の原油や天然ガスを輸入し続けている国々に対する働きかけも重要でしょう。特に中国とインドは温室効果ガスの大量排出国でもあり、ロシア産原油や天然ガスへの依存を減らし再生可能エネルギーへ切り替えることは、地球温暖化防止という面でも重要な貢献となります。
「戦争反対」を叫ぶことは重要ですが、それにとどまらず、いかに戦争を止めるための具体策を講じ、それを推し進めていくか。それこそ、今、9条を中心とする日本の平和主義が問われていることではないでしょうか。
(了)
【志葉からのお願い】本記事はいかがだったでしょうか?有意義な記事だと思われたら、是非、SNS等で拡散・シェアしていただけると幸いです。
すでに登録済みの方は こちら
提携媒体
コラボ実績
提携媒体・コラボ実績